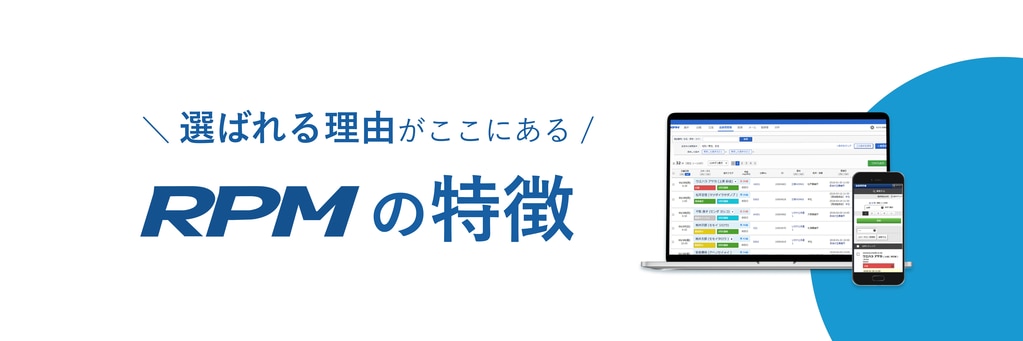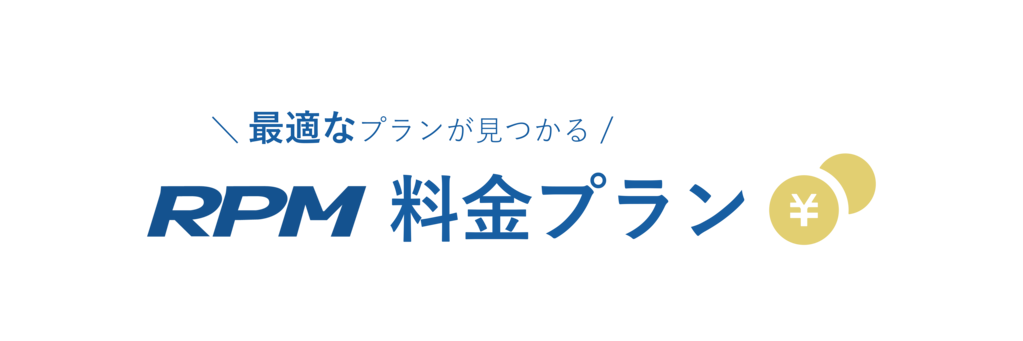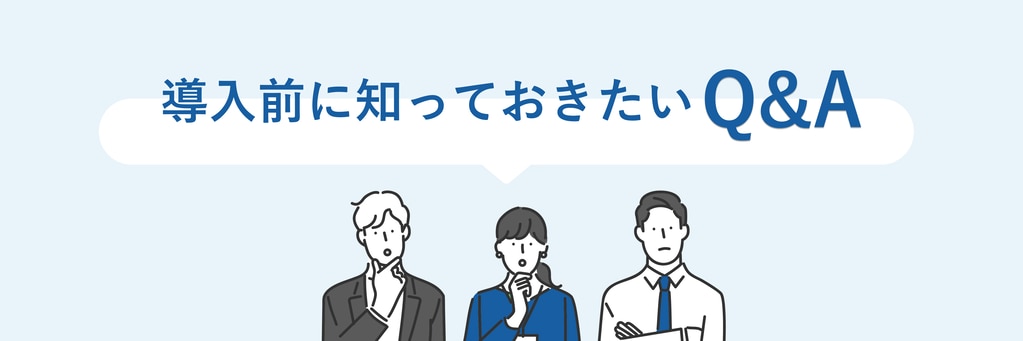通年採用のメリット・デメリットとは?導入を成功させる6つのコツ

より優秀な人材を確保するため、期間を区切った採用活動から通年採用に切り替えようと考えている採用担当者の方もいるのではないでしょうか。ただし通年採用には多くのメリットがある反面、いくつかのデメリットがあるので、しっかりと両者を検討することが大切です。
目次[非表示]
- 1.通年採用とは?一括採用との違い
- 2.なぜ通年採用が注目されているのか
- 3.通年採用のメリット
- 3.1.【企業】学生と出会う機会を増やせる
- 3.2.【企業】選考に時間をかけられる
- 3.3.【企業】内定辞退があっても必要な人材を確保できる
- 3.4.【学生】応募できるチャンスが増える
- 3.5.【学生】一社ごとに集中して就職活動できる
- 4.通年採用のデメリット
- 4.1.【企業】採用担当者の負担が増える
- 4.2.【企業】採用コストが高くなる可能性がある
- 4.3.【企業】一括採用とのバランスが難しい
- 4.4.【学生】高い能力を求められる
- 4.5.【学生】常にアンテナを張って就職活動に臨む必要がある
- 5.通年採用を成功させる6つのコツ
- 5.1.学生の理解を深める
- 5.2.競合分析を行う
- 5.3.入社時期・募集職種を限定する
- 5.4.応募条件を緩和する
- 5.5.新しい手法も取り入れてみる
- 5.6.採用管理システムを導入する
- 6.まとめ
通年採用とは?一括採用との違い

通年採用は一括採用と対比されることが多い採用手法です。それぞれどのようなものか概要を理解していても、特徴や採用活動の具体的な進め方が分かりにくいと感じている方もいるのではないでしょうか。
ここでは、通年採用とはどのようなものか、一括採用と比較したときの主な違いを詳しく解説します。一括採用の導入を検討しているのであれば、事前にチェックして自社のニーズに合った採用手法なのかを考えましょう。
通年採用の意味
時期を限定せず、1年を通じて採用活動を展開するのが通年採用です。通年採用を導入すると、新規事業の展開や既存チームの増員、欠員補充など必要に応じて求める人材を柔軟に採用できます。
人材を募集する際は、採用の必要性が生じた都度、求人広告を出稿する形が基本です。場合によっては、既存社員から知人を紹介してもらうリファラル採用など、公募以外の採用手法を併用するケースもあります。
一括採用との違い
通年採用と比較されることが多いのが、一括採用です。一括採用は同じ時期にその年に必要とされる人材をまとめて採用する手法で、一般的に新卒学生の選考で取り入れられています。
新卒一括採用では、必要な人員を事前に見積もって募集・採用しなければならず、柔軟性に欠けるのが難点といえるでしょう。通年採用では必要に応じた人材をその都度採用でき、採用活動や人員配置を効率化できます。
また、一括採用では募集時期に就職活動をしていない留学生などの人材を採用できませんが、通年採用では他の時期に就職活動している人材にもアプローチできる点が特徴です。
なぜ通年採用が注目されているのか

従来型の一括採用では、必要な人材を確保できない状況に陥っている企業も少なくありません。そこで社会的にも導入を後押ししているのが通年採用です。
ここでは、多くの企業が通年採用に注目している理由について詳しく見ていきましょう。
従来の一括採用では必要な人材を確保できない
従来型の新卒一括採用では、自社に必要な人材を確保できなくなっていることが背景にあります。新卒採用は就職協定によってスケジュールが定められていて、多くの企業が同時期に採用活動を展開するため、応募者からの人気が高い有名企業や大手企業が有利な仕組みです。
そのため、中小企業やベンチャー企業には応募者が集まりにくく、時期をずらして採用活動を展開する企業もあります。
他にも、日本の大学を卒業するタイミングに合わせて採用活動を展開する都合上、卒業時期が異なる国外の大学を卒業した人材や秋入学の人材を採用しにくいことも問題です。上記の問題を解決する方法の一つとして、一括採用を通年採用へと切り替えようとする動きが見られています。
経団連も通年採用を後押ししている
一般社団法人日本経済団体連合会(以下、経団連)と大学も、通年採用の導入を後押ししています。
また、政府も「2023(令和5)年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請について」で「卒業・終了後3年以内の既卒者に対して通年採用などさまざまな募集機会を積極的に提供すること」「2024年3月とは卒業・修了時期の異なる学生に対して通年採用などさまざまな募集機会の導入を検討すること」と、経済団体や業界団体に要請しているのが現状です。
すでに一括採用から通年採用へ切り替えている企業も多いことから、今後はさらにその流れが加速化すると考えられるでしょう。これまで一般的に行われていた4月入社を前提とした一括採用以外にも、秋採用をはじめとした別のタイミングに採用機会を提供する動きも進んでいます。
通年採用のメリット

これまでに行われていた採用活動の慣行にとらわれず、積極的に通年採用へ切り替えることには企業側・応募者側双方にメリットがあります。ここでは、企業側のメリット3つと応募者側のメリット2つを詳しく見ていきましょう。
【企業】学生と出会う機会を増やせる
新卒一括採用は、その年に日本の大学を卒業する人材にフォーカスした採用活動です。そのため、出会える人材が限られます。しかし通年採用を実施すれば、一括採用では出会えなかった以下の人材にもアプローチが可能です。
・国外の大学を卒業する留学生
・秋入学・秋卒業の学生
・既卒者・転職者
他にも、スケジュールが限られているために急いで就職活動を進めなければならず、自社の求人に気付いてもらえないことも考えられます。通年採用では余裕を持って採用活動を進められるため、より多くの人材にアプローチできる可能性が高まるでしょう。
【企業】選考に時間をかけられる
一括採用では採用活動を行える日程が決まっているため、その期間内に書類選考と複数回の面接、採用・不採用の判断を行わなければなりません。その点、通年採用であれば期間の制約がないのがメリットです。
必要に応じてある程度の時間を使って応募者のスキルや経験などを吟味し、本当に自社に合った人材かを見極められます。採用後のミスマッチを減らすためにも有用といえるでしょう。
【企業】内定辞退があっても必要な人材を確保できる
採用した人材が全員入社するとは限らず、採用後に辞退されてしまうこともあります。そのようなときには、欠員を補充するために新たな人材を募集しなければなりません。採用時期を限っていなければ、採用後の辞退が発生したときにも柔軟に対応できます。
入社後の短期離職があった場合も同様で、欠員が出たときに求人を出し、必要なスキルを有する人材を募集できるでしょう。一括採用では募集を再開しても人材が集まりにくい傾向にあることを考えると、必要に応じて人材を補充できる通年採用は大きな魅力です。
【学生】応募できるチャンスが増える
応募者側にとっては、限られた期間に一斉に求人を出す従来の方法に比べて応募チャンスが増えるのがメリットです。一括採用は期間が決められているため、複数の企業が同じ日に選考を実施するケースがあります。応募したい企業の選考が重なると、どちらを受けるか選ばなければなりません。
しかし、通年採用であれば選考タイミングが重なる可能性が低く、より多くの企業の選考を受けられます。余裕があるスケジュールを組んで就職活動を進められるのもメリットといえるでしょう。選考を受ける企業の増加は、自分に合った企業を吟味できる機会の創出をも意味します。
【学生】一社ごとに集中して就職活動できる
選考スケジュールが分散するため、一社ごとに時間をかけて企業研究し、選考に臨めるのもメリットです。限られた期間に複数企業に応募する一括採用では、時間の制約がある都合上、企業研究や選考の準備に充てられる時間が少なくなります。
時間をかけて準備できるようになれば、選考活動で自分のスキルや経験、入社意欲を十分アピールできるでしょう。
通年採用のデメリット

通年採用には数多くのメリットがありますが、一方で見逃せないデメリットもいくつかあります。ここでは、これから通年採用の導入を検討している企業が意識しておきたいデメリットを見ていきましょう。企業側のデメリットを3つ、応募者側のデメリットを2つ紹介します。
【企業】採用担当者の負担が増える
これまで一括採用をメインとしていた企業が通年採用へ切り替える場合、常に募集と選考を実施する体制を整えなければなりません。今まで一括採用時のみ採用活動に従事して、それ以外の時期は別の業務に携わっていたスタッフがメインの場合は、そのままでは通年採用に対応できない可能性もあります。
採用とそれ以外の業務を並行して行うとスケジュール管理が難しくなるため、採用活動の規模によっては専門のチームを立ち上げる必要があるでしょう。通年採用に移行するときは、社内の体制をきちんと整えることが大切です。
【企業】採用コストが高くなる可能性がある
通年採用を実施すると、人材の補充が必要になったタイミングで募集広告を出稿しなければなりません。特定の時期にまとめて募集広告を出稿する一括採用と比較すると、求人サイトや転職エージェントに支払うコストが増加する可能性が考えられます。転職イベントなどを活用する場合は、出展費用も忘れずに計算しましょう。
さらに、入社時期の分散もコスト増加につながります。研修も複数回実施しなければならず、その分の研修コストも増加する可能性が高いため、問題なく負担できるか試算することが大切です。
【企業】一括採用とのバランスが難しい
一括採用と通年採用を両立したい場合、バランスを取るのが難しくなりがちです。一括採用の時期に就職活動する応募者は多いと予想されるため、通年採用をメインにしたい場合でも一括採用への対策が求められます。場合によっては、一括採用で不採用になったときの滑り止めと考えてエントリーする応募者が増え、志望度合いや熱意が低い人材が集まりかねません。
社会全体で通年採用がメインになるまでの間は、通年採用で募集する人材を高いスキルが求められる職種に限定したり、中途採用をメインにしたりすることも一つの方法です。
【学生】高い能力を求められる
応募者のスキルや経験を吟味して自社に合う人材を採用できるのが通年採用のメリットですが、応募者側はそれに伴ってより高いスキルが求められます。一括採用であればある程度見逃してもらえていた部分であっても、通年採用ではより細かくチェックされる可能性も考えられるでしょう。
ただし、十分なスキルを有している応募者にとっては、自分のスキルをより魅力的にアピールするチャンスになります。より有利に就職活動を進めたいのであれば、普段から積極的にスキルアップを図ることが大切です。
【学生】常にアンテナを張って就職活動に臨む必要がある
通年採用には、一括採用のようにスケジュールにとらわれる必要がなく、企業が独自の採用活動を展開しやすい特徴があります。そのため、入社したい企業がいつ、どのような形で求人を出すのかが予測がつきにくい点がデメリットです。
応募者は情報を常に収集し、入社したい企業が求人を出していないか、出していたらどのような職種を求めているのかを調査することが大切です。
就職活動の時期が限られない反面、入社が決まるまでは常に情報収集し、意欲的に就職活動に取り組む姿勢が求められます。能動的に動けない応募者にとっては、一括採用より厳しい就職環境になると考えられるでしょう。
通年採用を成功させる6つのコツ

これから通年採用を導入しようと考えている企業は、成功させるためにもいくつかのポイントを押さえておく必要があります。ここからは、通年採用を成功させるために覚えておきたい6つのコツをチェックしていきましょう。
一括採用の延長という考えで取り組んでも、思ったような成果を出せない可能性があります。通年採用ならではの特徴を生かし、優秀な人材の確保に注力することが大切です。
学生の理解を深める
新卒採用の手法として通年採用を導入する場合、応募者候補となる学生の基本的な考えや動向を学ぶことが大切です。就職先に対して何を求めているのか、どのようなキャリアを望んでいるのか、何を考えて応募しているのかを知るように意識しましょう。
採用活動を実際に展開するときは、学生のスケジュールを意識することが欠かせません。実験や研究、論文の執筆などを考慮し、学業に影響が出ないような選考スケジュールを組みましょう。
競合分析を行う
社会的に通年採用が本格化し、メインの採用手法になると競合他社との人材の取り合いが発生します。そのため、競合他社の強みや動きの分析が欠かせません。競合他社と自社を比較したときの強みは何か、その強みを生かして市場で戦うにはどのような人材が必要かを考えましょう。
就職市場の動向もきちんと調査し、他社よりも有利に選考を進められるスケジュールを組むなどの対策も必要です。
入社時期・募集職種を限定する
一括採用をメインとしていた企業がいきなり通年採用を主軸にすると、変化に対応するのが難しくなります。そのため、最初は高いスキルが求められる専門職や欠員が発生しやすい職種を選んで先行導入したり、中途採用から移行したりするなど限定的に導入するのがおすすめです。
自社で通年採用を行うにあたって適した職種・部署がどのようなものなのかを考え、導入を進めましょう。
応募条件を緩和する
スケジュールを限定せずに採用活動を展開することで、多くの応募者にアプローチできるのが通年採用のメリットです。そのメリットを最大限に生かすためにも、応募条件の緩和を検討するとよいでしょう。
例えば、新卒・既卒を問わず同一の求人に応募できるようにしたり、学年を問わず応募を受け付けたりするなどです。高いスキルを有する人材を採用するため、インターンで成果を出した人材を優先的に選考対象にするのも一つの方法です。
新しい手法も取り入れてみる
既存の採用手法に限定せず、新たな手法を取り入れることも優秀な人材を確保する上で欠かせません。自社ならではのワークショップを開催したり、SNS上に求人広告を出稿したりするのは有用な方法です。
他にも、リファラル採用やヘッドハンティングなど、企業側から進んで優秀な人材を確保するための取り組みを展開してもよいでしょう。用いる採用手法によってアプローチできる人材の層は異なります。求める人材に応じて複数の方法を併用することが大切です。
採用管理システムを導入する
通年採用を実施すると採用活動の業務量が増えて担当者の負担が増すため、業務を可能な限り効率化する必要があります。そこで役立つのが採用管理システムです。
採用管理システムを導入すると、複数の求人媒体に出稿した広告や、応募者の情報・選考の進捗状況などの一元管理が可能です。応募者への連絡メールの送信をはじめとした定型業務の多くを自動化することも可能で、採用業務全体を大幅に効率化できるでしょう。
通年採用で増大した負担を軽減するためにも、早い段階で採用管理システムの導入を検討することをおすすめします。
まとめ

通年採用は、より優秀な人材を獲得する上で有効な取り組みです。しかし、通年採用にもいくつかのデメリットがあるため、それらを解消して効果を高めるための取り組みが欠かせません。
特に、増大する採用業務の効率を大幅に高めるためにも、採用管理システムを早めに導入することをおすすめします。
ゼクウでは多くの求人媒体と連携でき、採用に伴う雑務の多くを自動化できる採用管理システム「RPM」を提供しています。RPMを導入すると業務を効率化できるだけでなく、過去のデータを収集して分析できるようにもなります。今後の企業戦略を踏まえた優秀な人材を獲得する際にも役立つため、ぜひこの機会にRPMの導入をご検討ください。
▼RPMの特徴・強みをまとめたパンフレットは以下からダウンロードいただけます。
RPMのサービスの詳細はこちらで解説しています。ぜひご一読ください。
▼RPMの企業様向けページ