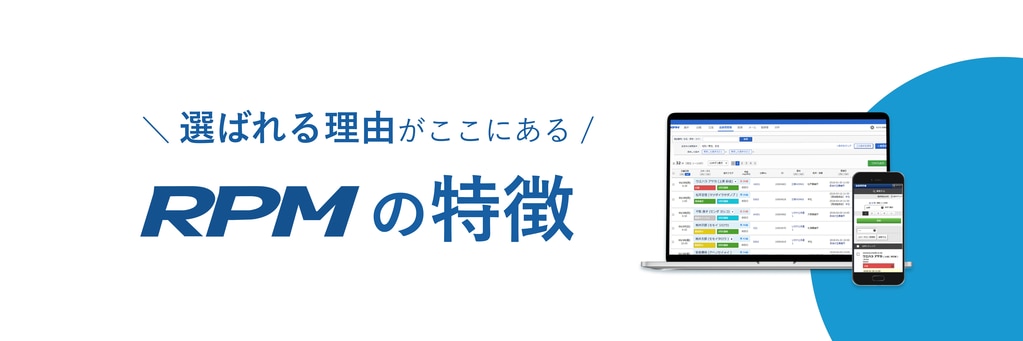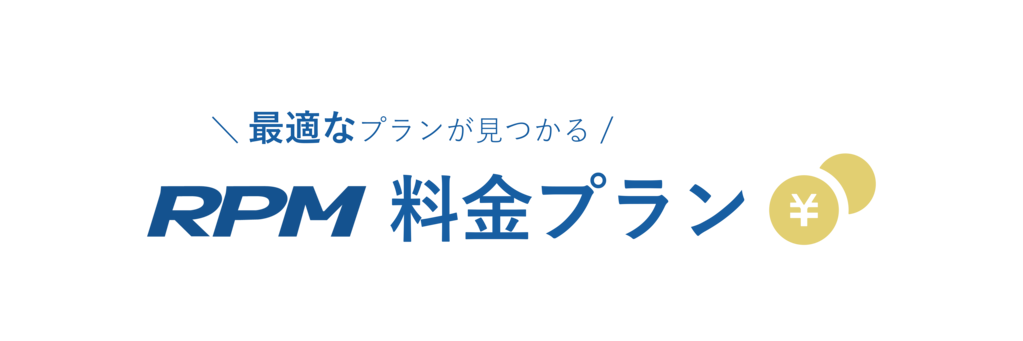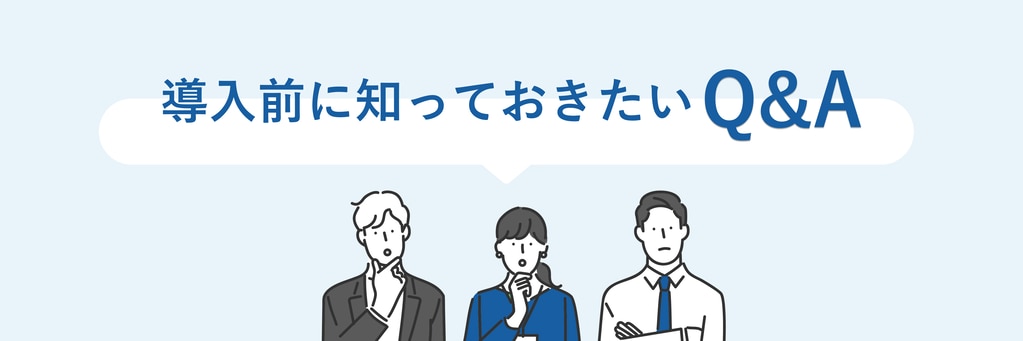選考を成功させる5つのポイント|新卒の採用選考フローと注意点も紹介

自社が求める人材を採用するには念入りな選考は欠かせません。この記事では、ミスマッチを防ぐために覚えておきたい採用のコツを紹介します。効果的な選考方法を理解することで、自社に合った人材をより効率的に採用できるでしょう。
目次[非表示]
- 1.選考とは?重要性を再確認
- 2.選考方法は主に3種類
- 3.新卒の採用選考フロー
- 3.1.募集活動
- 3.2.会社説明会
- 3.3.書類選考・筆記試験
- 3.4.面接
- 3.5.内定・内定者フォロー
- 4.選考における注意点
- 4.1.性別や障害で差別しない
- 4.2.センシティブな質問をしない
- 5.選考を成功させるポイント5つ
- 5.1.求める人物像を明確にする
- 5.2.採用手法を組み合わせる
- 5.3.話しやすい雰囲気作りをする
- 5.4.採用代行サービスを利用する
- 5.5.採用管理システムを導入する
- 6.選考管理システムならゼクウのRPM
- 6.1.最新の採用管理システム
- 6.2.応募者の情報を一元管理
- 6.3.取り込み媒体実績は400以上
- 7.まとめ
選考とは?重要性を再確認

選考とは、企業と応募者が互いに求める条件に合っているかを確認する場です。企業は応募者のスキルや経験が自社のニーズに合致しているか、応募者は待遇やキャリアパス、条件が合っているかをチェックします。
企業が採用・不採用を決める一方、応募者にも採用を受け入れるか辞退するか選択する権利があるため、自社が求める人材を逃さないようにしなければなりません。
選考では自社の魅力を積極的にアピールし、応募者が求める待遇やキャリアパスを可能な限り実現できるように努力する必要があります。応募者が必要なスキルや経験を有していて、入社後に発揮できそうか見極めることも大切です。
選考方法は主に3種類

採用活動における選考には、「書類選考」「筆記試験」「面接試験」の3種類があります。いずれも応募者のことを詳しく知り、自社との相性を判断する上で大切です。ここでは、採用担当者がそれぞれの選考で注目したいポイントについて解説します。
書類選考
企業が指定する書類を応募者に提出してもらい、記載された内容に基づいて選考を進めるのが書類選考です。選考の最初の段階に位置付けられることが多く、応募者が基本的な応募条件を満たしているかを判断します。
書類選考では、エントリーシートや履歴書、職務経歴書を使用するのが一般的です。オンラインや郵送といった自社に合った方法で提出してもらいましょう。選考担当者は学歴や職歴、保有資格が募集条件に合致しているか確認します。
筆記試験
企業によっては、業務に必要な知識や一般的なビジネスマナーを習得しているかを確認する目的で筆記試験を実施します。内容は、専門分野や一般常識などさまざまです。適性試験で自社の業務に対する適性を判断することもあります。
筆記試験は実施しない企業もあるため、自社の採用活動に必要か見極めましょう。筆記試験ではなくCBTで実施する企業もあります。効率化を考えているのであれば、導入を検討してもよいでしょう。
面接試験
面接試験は応募者と面接担当者が直接対面し、会話することで応募者が採用に値するか判断する試験です。集団面接や個別面接をはじめとしたいくつかの手法があるため、応募者の数や選考で重視する要素に応じて適切な手法を用いましょう。
面接は1回ではなく、複数回行うこともあります。複数回に及ぶ面接の場合、途中で評価の軸がぶれるとミスマッチを誘発するため、選考基準を明確に決めることが大切です。
新卒の採用選考フロー

企業の採用活動はいくつかの段階に分かれます。自社に必要な人材を確保するには、採用活動の流れを理解した上でそれぞれの段階に応じて施策を考え、実行することが大切です。ここでは、新卒採用を例にして、具体的な選考フローとそれぞれの段階で何をするか解説します。
募集活動
募集活動は選考における最初の段階で、求人広告を出稿し、応募者を探す活動です。また、応募者を探す取り組み全般を指す場合もあります。
自社が求める人材に応じて、求人サイトや転職エージェントの中から適切な媒体を選ぶことが必要です。自社サイトやオウンドメディア、SNSによる求人活動やリファラル採用を併用し、母集団を形成しましょう。
会社説明会
募集活動で集まった応募者に対して、会社説明会を開催します。会社説明会は、自社のビジネススタイルやビジョン、具体的な仕事内容を紹介し、応募者の理解度を深める活動です。自社の魅力を伝えることで、応募者の入社意欲を高めてもらいましょう。
会社説明会と選考を並行するケースや、オンラインで1次選考を実施した後に会社説明会を開催するケースもあります。採用予定数と応募者数のバランス、採用活動全体の効率を考え、どの形で実施するか検討するとよいでしょう。
書類選考・筆記試験
選考の第一段階として実施するのが、書類選考や筆記試験です。書類選考ではエントリーシートや履歴書、成績証明書といった書類を提出してもらい、自社が求める人材の条件に適合しているか判断します。
提出書類を決めたら、提出方法も伝えましょう。会社説明会で提出する方法や指定日までに郵送する方法、オンラインで提出する方法などさまざまです。選考担当者が管理しやすく、応募者の負担が少ない方法を選ぶとよいでしょう。
筆記試験は、一般常識や専門知識、ビジネスマナーなど、自社が求める知識やスキルを有しているかを判断する試験です。試験の日程や内容、実施方法を決めて応募者に事前に伝えます。
面接
書類選考や筆記試験で採用候補者を絞ったら、面接試験に進みましょう。面接試験は応募者一人一人に会い、本当に採用してよいか判断する場です。面接には、集団面接や個別面接、グループディスカッションといったさまざまな方法があります。採用担当者の業務負荷や面接にかけられるリソースに応じて方法を検討しましょう。
面接の回数は企業によって異なります。複数回実施する場合、1回目は集団面接、2回目以降は個別面接にするなど、複数の手法を使い分けてもよいでしょう。
内定・内定者フォロー
全ての選考が終了し、合格者が決まったら内定を出します。内定は「応募者に対して自社で採用したいとオファーすること」を意味し、応募者が受諾したら成立です。ただし、一度内定を受諾しても、入社までに状況や気持ちが変わって辞退することも考えられます。
内定辞退を防ぐためにも、入社までの間に定期的な内定者研修や交流会を実施するとよいでしょう。アクティビティを通じて内定者同士の交流を促したり自社に対する理解を深めたりすることで、内定ブルーを防いで入社意欲が高い状態を保ちやすくなります。
選考における注意点

選考を進めるときには、面接でNGとされる質問をしないといった一定の配慮が必要です。中には、法律で禁止されていることもあるため、十分に注意しましょう。ここでは、選考の際に注意したいポイントを2つ紹介します。
性別や障害で差別しない
募集や選考では、年齢や性別、障害の有無によって差別することが禁止されています。これは、就職の機会は全ての人に対して均等に開かれていなければならないという雇用対策法や男女雇用機会均等法の考えに基づくものです。
したがって、実際の選考においても基本的人権に配慮した基準を設けなければなりません。スキルや経験など、「職務を遂行する上で求められる条件を満たしているか」を軸にするとよいでしょう。
センシティブな質問をしない
仕事に直接関係ないセンシティブな質問をするのもNGです。例えば、出身地や家族構成のような本人に責任がない内容が含まれます。他にも、信仰する宗教や支持政党をはじめとした思想・信条に関する質問もNGです。
これらの質問は業務に関係ないだけでなく、内容によっては基本的人権の侵害にもなりかねません。選考担当者の知識不足で質問することがないように、事前に質問を決めて共有しておくとよいでしょう。
選考を成功させるポイント5つ

選考は正しい基準に基づいて適切に行ってこそ効果を発揮します。採用基準を明確に定めて、適した選考手法を使用し、効率的に運用することが大切です。ここでは、選考で自社が求める人材を採用するために覚えておきたいポイントを5つ紹介します。
求める人物像を明確にする
新たな人材を採用するときには、自社が求める人物像を明確にしましょう。応募者に求めるスキルレベルや経験など、採用の軸となるポイントに関して選考基準を決めて、書類選考や面接では基準に基づいて応募者を評価します。
選考を進める中で求める人物像や基準がぶれると、ミスマッチや認識のずれにつながる恐れがあります。しっかりと明文化して共有するとよいでしょう。
採用手法を組み合わせる
採用手法は、求人サイトや転職エージェントの利用、リファラル採用、ヘッドハンティングと多種多様です。例えば、専門的なスキルを有する人材を求めるのであれば、ヘッドハンティングや特定の分野に特化した転職エージェントを利用するとよいでしょう。
ただし、採用手法にはそれぞれメリット・デメリットがあります。特定の手法のみを使用するのではなく、デメリットを補えるような別の採用手法を併用するのがおすすめです。
話しやすい雰囲気作りをする
選考で大きなウェイトを占める面接では、応募者をより深く知ることが重要です。応募者が緊張していると思ったように会話が弾まないため、話しやすい雰囲気作りを心掛けましょう。
面接の最初にアイスブレイクを盛り込むなど、どうしたら応募者の本心を引き出せるかを考えます。面接が良い雰囲気で進めば、応募者の志望度合いや入社意欲も高まるでしょう。
採用代行サービスを利用する
スピーディーな選考を実現するには、選考担当者の業務量を削減して、業務全体を効率化することが欠かせません。
選考の効率化には、採用業務を委託できる採用代行サービスを利用して一部の業務をアウトソースするのがおすすめです。応募者の管理や連絡といった雑務を委託することで、採用担当者の負担が軽減し、書類選考や面接といったコア業務に専念できます。
採用管理システムを導入する
採用活動を効率化するもうひとつの方法が、採用管理システムの導入です。採用管理システムは、求人媒体の管理や応募者情報の取り扱い、スケジュールの調整といった雑務を自動化し、業務効率を大幅に高めるのに役立ちます。
採用管理システムを導入することで、担当者の負担を大きく軽減し、スピーディーな選考が可能です。一定のコストがかかりますが、それ以上の効果に期待できるため積極的に利用することをおすすめします。
選考管理システムならゼクウのRPM

採用管理システムを導入するのであれば、多くの求人媒体に対応し、必要な機能が充実しているものを選ぶとよいでしょう。数ある採用管理システムの中でも、ゼクウのRPMの導入をご検討ください。RPMは充実した機能で選考担当者の業務負担を軽減します。
最新の採用管理システム
RPMはクラウド型の採用管理システムです。利用者は特別な手続きやアップデート料金を支払うことなく最新の機能を利用でき、日々変化する採用活動のトレンドに対応できます。
今後も1年間に4回以上のアップデートを予定しており、使いやすさを重視したUI/UXの改善や新たな機能の実装、既存機能の拡張を目指しています。最新機能をいち早く使いたいと考えている方にもおすすめです。
応募者の情報を一元管理
応募者の情報を集約して一元管理し、連絡を自動化できるのも大きなメリットといえるでしょう。面接のセッティングや進捗状況の可視化も可能で、複数の採用担当者が同時に関わる際に役立ちます。
情報をシステム上で確認できるため、選考がどこまで進んでいるのか、次に何をしなければならないかをすぐに理解できるでしょう。対応漏れを予防する効果にも期待できます。
取り込み媒体実績は400以上
採用では複数の求人媒体を併用するケースが多いため、多数の媒体から情報を取り込めるシステムが必要です。手動で情報を管理するとミスが発生しやすく、業務効率が大きく低下するでしょう。RPMは400以上の求人媒体に対応しており、一般的な求人媒体の95%以上で自動取り込みが可能です。
まとめ

選考は会社説明や書類選考、面接と多段階に分かれており、必要な人材を採用するには明確な基準を決めて実施する必要があります。スピーディーに選考を進めるには採用業務の効率化が欠かせません。
選考の効率化には、雑務の多くを自動化できる採用管理システムの導入がおすすめです。ゼクウでは、多くの求人媒体と連携(約95%の媒体をカバー)可能で、スケジュール調整や連絡を自動化できるRPMを提供しています。頻繁にアップデートを実施し、最新の機能や採用トレンドに対応するシステムです。採用管理システムを導入したいと考えている方は、ぜひRPMをご検討ください。
▼RPMの特徴・強みをまとめたパンフレットは以下からダウンロードいただけます。
RPMのサービスの詳細はこちらで解説しています。ぜひご一読ください。
▼RPMの企業様向けページ